
記事前半では、OTA ART GARDEN (以下OAG) プロデューサーで、建物のオーナーでもある中村政久さんに、生まれ変わるまでの場所のヒストリーを伺いました。記事後半は、生まれ変わったOAGを中村さんにご案内いただきながら建物巡りとアートを楽しんだ様子をお届けします。

韮川駅前に面しているのは、店舗として使われていた母屋です。まず出入り口で迎えてくれる扉は、重厚な蔵の内扉を中村さんがリデザインしたもの。元々は沼田にあった蔵の扉を譲り受け、中村さんが古材を組み合わせてリデザイン / リメイクしました。この後、さらにアーティストに依頼した板絵が組み込まれるのですが、この場所で出会った21歳の若き地元アーティストの作品だそうです。

「この場所ができてから、人との繋がりがさらに広がったのを実感してます。地元のアーティストも良い感性を持ってる若い人が結構多くて、作品を見せにきてくれたりしてね。そういう若手と東京のアート関係者が繋がる手伝いもできました。JIA日本建築大賞にノミネートされたことで有名建築家もたくさん見に来てくれたし、地元の建築関係の人とも色々と繋がることができてよかったです。この場所の力のおかげで僕自身も色々な人と出会えてます。」


母屋の間取りは、土間を広くしたところもありますがほぼ昔のままです。天井は一部だけ残し小屋組をあらわにすることで空間に広がりが出ました。建具も元々のものを活かしながら障子紙を取って抜け感を出したり、モダンな家具や装飾とあえてのミスマッチを楽しむなど、中村さんのセンスと遊び心がそこかしこに表れています。例えば、欄間の格子は、昔ネズミに齧られ欠けてしまったことを逆手に、反対側の格子もわざと取って対称的にリデザイン。
「この先、格子が傷んでもっと欠けちゃうようなことがあれば、わざとモンドリアン風の格子にしちゃっても面白いよね。」と楽しい企みもあるようです。

米蔵で使われていた木材を使って家具もリメイク。蔵のなかで、かつて俵を担いだ人夫さんが渡っていた丈夫で立派な橋材を、テーブルに生まれ変わらせました。
減築し新たに壁を作り直した部分は意外なところに窓が作られ、茶室のにじり口をイメージしているそうですが、ホルヘ准教授の日本建築への新鮮な視点が反映されていて興味深いところです。

西側のガラス戸の向こうは、隣地とこちらを区切る古いブロック塀が視界を塞いでしまっていましたが、塀の補強を兼ねてDIYで竹を張ることで竹垣風に。窓から見える景色もちょっとした工夫で雰囲気が変わります。

渡り廊下を通って昭和中期に増築した2階家へ進むと、広々としたキッチンとダイニングスペースがあり、柔らかな存在感で迎えてくれる大きなダイニングテーブルが印象的です。耐震的に既存の柱を取ることができなかったため、木工作家さんが制作した2枚の大きな天板で柱を挟み、オリジナルのテーブルをスペースの中心に組み立てることで、建物の構造を変えずにゆとりある空間が実現しました。食器棚にリメイクされた和箪笥は、センスが光る中村さんのDIY仕事です。


2階の和室には工芸作品も飾られています。昔の和室でよく用いられてきた砂壁は古くなるとポロポロと崩れ落ちてきてしまうので、シーラーで固めました。普通ならムラなくきれいに塗りたいところですが、「ラフなほうが味が出るかも。」との中村さんの閃めきで遊び心あるアートな仕上がりになっています。


同じく2階のレトロな洋間には、中村さんの仕事仲間だった永井博さん、湯村輝彦さん、河村要助さん、日比野克彦さんなどの錚々たるイラストレーターの原画などが置かれ、ポップな雰囲気です。
この2階家は、予算の関係で中村さんが最もDIYで直したところが多い建物で個人的な思い入れは一番強いとのことです。
「時間がかかったのは大変だったけれど、苦労と感じることはなく総じて面白かったですね。塗装とか漆喰も最初は下手なんだけど、壁半分くらいやったところでコツもわかってきて、どんどん上手になっていくのが自分でわかるんですよ。」
次は庭に出て、精米加工場や米蔵を直したアトリエ群を案内していただきました。屋根は重たい瓦からガルバリウムに葺替えるとともに天窓をつけました。

精米加工場の崩れていた土壁は撤去して、既存躯体とポリカーボネート波板を組み合わせた壁となり、自然光の入る明るく軽やかな建物に生まれ変わりました。波板と躯体の美しいピッチと重なり方に、ホルヘ准教授の建築家としてのこだわりが込められています。また、コンクリートだった地面に土を入れ芝を敷くことで、庭との連続性を持つ開放的な空間に。紙で立体作品を作るアーティストがここで大きな作品を制作する計画もあるそうです。
米蔵の前に張り出した大きい屋根の下の屋外空間は良い風が通り抜けるそうです。コンサートなどのイベント会場としても使われていますが、特に印象的だったのは、地元中学校の同窓会の会場として使われた時。数十の席を並べて80歳のおじいちゃんおばあちゃんが一堂に集まり楽しく過ごしたそうです。面白く使ってもらった光景だったなと、中村さんは楽しそうに振り返ります。
蔵の中にはサイズの大きな絵画作品や彫刻が並んでいます。大きな作品を作るアーティストは保管スペースに難儀するので、アーティストから頼られてOAGに作品がやってくることもあるそうです。
この日は、蔵の扉を開けた正面には、独自技法で注目されている新進気鋭の日本画家・木下めいこさんの蓮を描いた作品が掛けられていました。古い米蔵なので季節によっては建物内に蔦が這うこともあるそうです。蓮の絵のそばに蔦が這うという、何とも面白い飾り方もOAGでは実現できてしまいます。

「僕自身は、アートをいわゆる美術館のようなカチッとした中に飾るのは好きじゃないんですよ。彫刻家の安田侃さんは野外に作品を置いて触れてもらうようにしているんですけど、安田さんと対談した時に僕も影響を受けて。米蔵での展示の仕方もそうだし、ギャラリーやパブリックキッチンでも様々なところに何気なくアートが入っているようにな置き方をしています。生活の風景の中に絵があるな、くらいの感じでいい。もし、見に来た人が『うちでもあんなふうにアートを飾れたらいいな。』と思ってもらえたらなお良いですね。」
隣の壁面には、OAGが生まれる縁のきっかけとなった画家・井上悦治さんのアクリル絵画作品が掛けられ、その前には彫刻家・中野滋さんの作品が並んでいます。その中には、中村さんが手がけたJR東海のキャンペーンポスター撮影のために作られた彫刻もあります。3ヵ月で6体を制作するという中村さんのタイトな発注に応えるため、中野さんが親友の故・舟越桂さんと協働し、中野さんが彫った像に舟越さんが色彩をつけたそうです。


そんなアート通も唸る貴重なエピソードも色々と教えてもらいつつ、OAG巡りを楽しませていただきました。
この春のOAGでは3月15日(土)〜4月13日(日)の会期で、中村さん、井上さん、中野さんたち藝大時代の友人たちによるグループ展「10人10色展」が開催されています。藝大卒業から50年、美術界で活躍する10人のアーティストの様々な世界観を見ることができます。取材当時と並ぶ作品がまた変わってきていると思いますが、この機会にぜひ足を運んでいただきたいです。
またギャラリー内に「Magnolia Coffee Roasters OAG」が3月からオープンしました。太田市内でスペシャリティーコーヒーの焙煎と豆販売を行う専門店「Magnolia Coffee Roasters」の新たなお店として、コーヒー豆が買えるのはもちろんのこと、OAGの中でコーヒーを飲むこともできます。

アートやクラフトやワークショップなど何かを生み出す人の繋がりが、この場所からもっと広がって行ってほしい。加えて、アートが入り口でなくても気軽に寄ってもらえたらと中村さんは願っています。
「OAGの表に設けたベンチが、近頃は色々と微笑ましい使われ方をしていて嬉しいんですよ。幼稚園の保護者さんがおしゃべりをしながらバスを待っていたり、高校生のカップルが仲良く過ごしていたり、韮川駅に降り立った親子が帰宅する前にここのベンチで語り合っていたり。そのうちに中にも入ってきてもらえたらいいですね。」

中村さんはOAGの場所づくりがきっかけとなり、そのノウハウを活かした古民家再生ユニットも結成。他の建物への提案も始めているそうです。今後の展望としては、様々な個性を持つ古材からインスパイアを受けて、現代の美意識合う家具にリデザインするプロジェクトを企画しています。そのほかにも、アイデアもやりたいことも、尽きることなく湧いてきているそうです。
「OAGもリノベーションは一旦仕上がったけど、『完成』ではないんです。アイデアがいくらでも湧いてきて、絶えずどこかをいじっているんですよね。」
OTA ART GARDEN は、柔らかく光がまわる古民家ならではの空間で、この場所の感性と共鳴するたくさんの人を迎え入れてくれます。
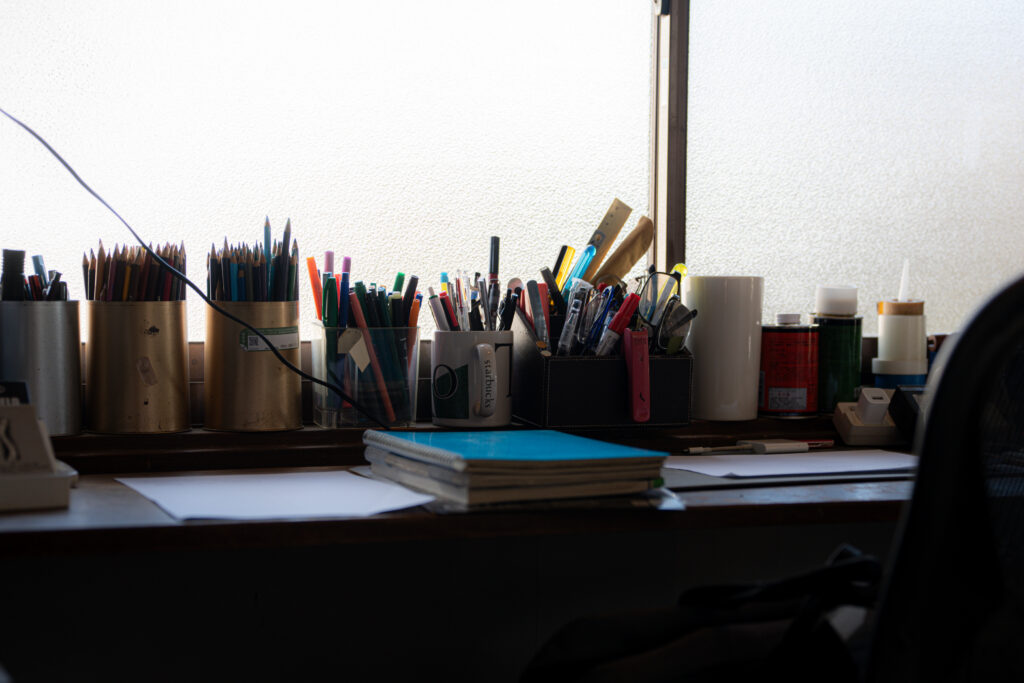
Contact お問い合わせ
古民家を所有している方
空き古民家、どうしよう。古民家の処分(売却、賃貸借)てどうすればいいの?
古民家を活用したい方
古民家を活用してみたいけど、購入?賃貸?どちらがいい?
民間事業者の方
行政、まちづくり会社、不動産会社、設計事務所、工務店、移住コーディネーター等。
コミンカコナイカ事業にチームメンバーとして参画しませんか?

